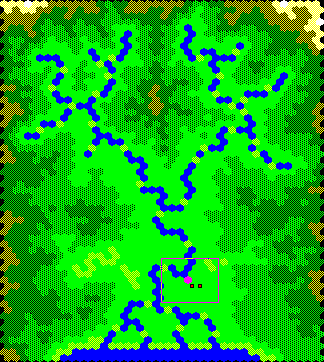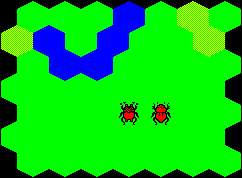2000年特別企画 歴代パソコンでのリレー飼育
1999年1月:PC-9801VM2
← 2000年特別企画のページへ
← ツノヤハズのページへ
…と思い付いたのが1999年の正月,NECのPC-9801VM2で飼育の準備をはじめました.
この機械は最近までパソコン通信に使っていたので,まだまだ現役です.博多のパソコン屋のジャンケン大会で勝手購入の権利を獲得した40MBの外付けハードディスクをシステムドライブにMS-DOS3.3Bが立ち上がります.メニューはDOSに付属のmenu.comの罫線の色指定をエコロジーで書き換えたやつ,中身はmenu.mnuをマイフェスで書き換えたものです.

PC-9801VM2
外付けの3.5インチFDDは1.25MBだけしか読み書きできないやつです.ダマスケという640KB用のソフトがついてましたけどね.で,今となっては貴重な内蔵5インチFDDは2基とも活きているのですが,それぞれ個性ができてしまい.B:ドライブで書き込んだファイルがC:では読めない,といったことがあります.
ツノヤハズの飼育システムの最初のやつは,この機械でQuickBASIC4.5で作りました.そのころはわからなかったんですが,QB45のエディタのインターフェイスは先進的だったんですね.画面はテキストでも操作はGUIでした.カットアンドペイストはこいつに教わりました.でも,それで作ったDEME(ツノヤハズ飼育システム)はすべてキーボードをコマンドボタンとするようなものです.
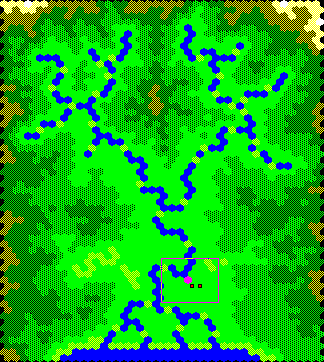
飼育地形全景
飼育に使う地形ファイル上図のようには"Gulf.trr"という,山を削って平野を作って小さな水系みたいなやつです.側は所々渡れるようになっています.しかしそれでも,川を挟んで異なる型が対峙する状況がよく生じます.そういう実績のある,いわば鑑賞用には適した地形です.
既存の設定ファイルを少しいじって,東の平野に1ペアいる状態を作り,4日午後9時すぎに飼育をスタートしました.
ところで,このシステムでは飼育中の画面をキャプチャーすることができません.印刷する機能は付けているのですが,色の違いを白黒パターンで表現するもので,ファイルに落とすことはできません.ここで示している図は別の98のWindows上DOSプロンプトで再現したものです.
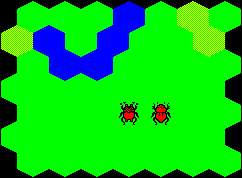
初代のペア
10世代ほど様子をみて全滅してないことを確認した上で100世代ごとにセーブするよう設定,まわしっぱなしにしておきました.次の日の夕方には5,000世代目に到達していました.23〜4分で100世代進みます.フロッピーの残量を見て10,000まで行けそうだと考え,さらに高速世代更新にしました.6日の夜,見てみるとフロッピーが満杯になってシステムが停止していました.セーブしそこなっている最後の世代のファイルを捨ててました.こうして9,300世代までの記録が残りました.次のフロッピーに植えついて,ぼちぼち続けていくことにしました.
この後もフロッピーが満杯になったのを気づかなかったりして,結局100,000世代まで飼育しました.最後の100世代は5インチにセーブさせたら94世代分しか入らず,それであきらめて書き込み保護のシールを貼りました.
残った記録をあらためて調べてみると,途中3回ほど2〜3種に分化した時期がありました.それ以外も川を挟んで違う型が見られ,それらしいです.
↑ 文頭へ ↑